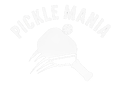ピックルボールを始めたばかりのとき、プレイ中に「サーブの順番がよくわからない…」と感じたことはありませんか?
ピックルボールのサーブにはダブルスやシングルスで異なる独自のルールがあり、サーブ権の移動や得点の仕組みも少し複雑です。
サーバーが何回打つのか、どの位置から打つのかという疑問に加え、効果的なレシーブやボレーのコツ、初心者向けのドロップサーブの存在など、覚えるべき点は少なくありません。
この記事ではピックルボールのサーブに関する順番やその他ルールを、初心者の方にも分かりやすく徹底的に解説します。
【記事のポイント】
- サーブの基本的な順番やルールがわかる
- ダブルスとシングルスの違いを理解できる
- サーブ権や得点の仕組みが明確になる
- サーブを活かす戦略的なコツが身につく
ピックルボールのサーブの順番や基本ルール
- サーブの順番に関わる基本ルール
- ダブルスにおけるサーブの進め方
- シングルスにおけるサーブの進め方
- サーブ権の移動するタイミングとは
- サーバーはサーブを何回打つ?
- サーブ側のみに与えられる得点
サーブの順番に関わる基本ルール
ピックルボールのサーブ順を正確に理解するためには、まずゲーム全体の流れを決定づけるいくつかの大前提となるルールを把握しておく必要があります。
特にピックルボールの独自性を際立たせているのが「ツーバウンドルール」と「ノンボレーゾーン」の存在です。これらはサーブから始まる一連のプレーに深く関わっており、サーブの順番と合わせて覚えることで試合の戦略性が格段に理解しやすくなります。
ツーバウンドルールとはサーブされたボール(1バウンド目)と、それに対するリターン(2バウンド目)は必ずそれぞれのコートで一度バウンドさせてから返球しなければならない、という国際的にも定められたルールです。
これによりサーブ直後にネットに詰めて強力なボレーを叩き込むといった速攻戦術が封じられ、自然とラリーの応酬が生まれます。このルールこそがピックルボールが年齢や経験を問わず楽しめるスポーツである理由の一つと言えるでしょう。
そしてもう一つの重要なルールが、ノンボレーゾーン(通称:キッチン)です。これはネットの両側に設置された横6.10m×縦2.13mのエリアを指します。
このエリア内、あるいはエリアのライン上に体の一部でも触れている状態ではノーバウンドのボール、つまりボレーを打つことが禁じられています。
もし打ってしまった場合はフォールト(ミス)となりますが、一度コートでバウンドしたボールであれば、プレーヤーはノンボレーゾーンに踏み込んで返球することが可能です。
このエリアの存在が、ネット際での繊細なボールコントロール(ディンク)の応酬という、ピックルボールならではの攻防を生み出しています。
サーブ後のプレーを支える2大基本ルール
- ツーバウンドルール:サーブとリターンの2球は、必ずバウンドさせてからプレーを続行する。これにより誰でもラリーに参加しやすくなる。
- ノンボレーゾーン:ネット際の特定エリアではボレーができない。これにより至近距離からの強打を防ぎ、安全かつ戦略的なプレーを促進する。
これらの基本ルールが、サーブから始まるポイント全体の流れをデザインしています。サーブの順番という手順だけでなく、その後のプレーにどのような制約と可能性があるのかをセットで理解することが、ピックルボール上達への確実な一歩となります。
ダブルスにおけるサーブの進め方
ピックルボールの試合形式として最もポピュラーなダブルスでは、サーブの順番に少し複雑ながらも合理的なルールが採用されています。
最初は戸惑うかもしれませんが、一度流れを覚えてしまえばゲームの状況を正確に把握しながらプレーできるようになります。
ゲーム開始時の特別なルール:ファーストサーバーダウン
ピックルボールのダブルスでは、ゲームを公平に始めるための特別な初期ルールが存在します。
通常、各チームはパートナー2人分のサーブ権を持ちますが、ゲーム開始後の最初のサーブ権を得たチームだけは、サーバーが1人しかサーブできません。
この最初のサーバーが1回でもフォールトを犯すと、その時点で「サイドアウト」となり、すぐに相手チームへサーブ権が移行します。これは「ファーストサーバーダウン」と呼ばれるルールです。
この特別ルールをスコアコールで明確にするため、ゲーム開始時のコールは「0-0-2(ゼロ-ゼロ-ツー)」から始まります。これは「自チーム0点 – 相手チーム0点 – サーバーは2人目」という意味です。
最初のサーバーをあえて「2人目」とコールすることで、「このサーバーがミスをしたら、もう次のサーバーはおらず、サイドアウトになりますよ」という状況を全プレーヤーで共有する仕組みになっています。
サーバーの交代とサイドの移動:得点を重ねる流れ
ゲーム開始時の最初のサーブ権以降は、各チームのプレーヤー2人が順番にサーバーを務めます。その流れは得点とフォールトに応じて決まっています。
| ステップ | 状況 | アクション |
|---|---|---|
| ① | サイドアウトでサーブ権を獲得 | その時点で右サイド(偶数サイド)にいるプレーヤーが1人目のサーバーとしてサーブを開始する。 |
| ② | サーブ側が得点する | 得点した同じサーバーが今度は左サイド(奇数サイド)へ移動して次のサーブを打つ。 |
| ③ | さらに得点が続く | 同じサーバーが得点のたびに左右のサイドを交互に移動しながらサーブを続ける。 |
| ④ | 1人目のサーバーがフォールトする | サーブ権がパートナー(2人目のサーバー)に移る。 |
| ⑤ | 2人目のサーブ開始 | 2人目のサーバーは1人目が最後にサーブを打ったサイドとは反対側からサーブを開始する。 |
| ⑥ | 2人目のサーバーがフォールトする | 「サイドアウト」となりサーブ権が相手チームに移る。(相手チームはステップ①から開始) |
注意:ローカルルールの確認
一部の古いルール解説や地域独自のハウスルールでは、自チームのスコアの偶数・奇数によって1人目のサーバーが変わる、といった複雑なルールが採用されていることがあります。
しかし、USA Pickleballの公式ルールをはじめとする現行の主要ルールでは、サーブ権獲得時に右サイドにいるプレーヤーが最初のサーバーとなるのが標準です。初めてプレーする場所では事前にローカルルールを確認しておくと混乱を防げます。
スコアコールは「自チームの得点 – 相手チームの得点 – サーバー番号(1 or 2)」の3つの数字を明確に発声することがマナーです。これにより全プレーヤーがゲームの状況を正確に把握し、スムーズな進行が可能になります。
シングルスにおけるサーブの進め方
シングルスのサーブ順は、ダブルスに比べて非常にシンプルです。パートナーがいないためサーバーの交代がなく、サーブを打つべきサイドは常に自分自身のスコアによって自動的に決まります。
このルールは初心者でも直感的に理解しやすいのが特徴です。
- 自分のスコアが0点または偶数(2, 4, 6…)の場合:コートの右サイド(偶数サイド)からサーブを打ちます。
- 自分のスコアが奇数(1, 3, 5…)の場合:コートの左サイド(奇数サイド)からサーブを打ちます。
具体的なゲームの流れを追ってみましょう。ゲーム開始時のスコアは0-0(偶数)なので、サーバーは右サイドからサーブを開始します。
ラリーに勝って得点しスコアが1-0(奇数)になると、サーバーは次のサーブを左サイドから打ちます。さらに得点して2-0(偶数)になれば再び右サイドに戻ってサーブを続けます。
このように、得点を重ねる限りサーバーは左右のサイドを移動しながら、常に自分のスコアに対応した正しいサイドからサーブを打ち続けることになります。
一度フォールトして相手にサーブ権が移り、その後ラリーに勝って再びサーブ権を取り返した際も、この原則は変わりません。
その時点での自分のスコアを確認し、それが偶数であれば右サイドから、奇数であれば左サイドからサーブを再開します。
シングルスはコート全体を1人でカバーする必要があるため体力的な負担は大きいですが、サーブの順番に関しては自分のスコアだけを覚えておけばよいので、ルールは非常に明快です。ダブルスの複雑なサーバー交代に慣れる前の練習としても最適かもしれません。
サーブ権の移動するタイミングとは
ピックルボールにおいてゲームの流れを左右する重要な概念が「サーブ権の移動」です。これはサーブ権を持っているチーム(またはプレーヤー)がラリーに敗北した、すなわちフォールト(ルール違反やミス)を犯したタイミングで発生します。
フォールトと見なされるプレーは多岐にわたりますが、サーブ権の移動に直結する主な例としては以下のようなものがあります。
主なフォールトの例
- サーブ時のミス:サーブがネットにかかる、対角線上の正しいサービスエリアに入らない、サーブ時にラインを踏む(フットフォルト)。
- ツーバウンドルールの違反:サーブまたはリターンを、バウンドさせずにボレーで返球してしまう。
- ノンボレーゾーンでの違反:ゾーン内またはライン上でボレーを打つ、ボレーの勢いでゾーン内に踏み込んでしまう。
- アウト:打ったボールが相手コートのライン外に着地する。
- その他:ラリー中にボールが自分の身体や衣服に触れる、ネットやポストに身体やパドルが触れる。
サーブ側のチームがこれらのフォールトを犯すと、サーブ権に以下のような変動が起こります。
ダブルスの場合:
チームには2回のサーブチャンスがあります。1人目のサーバーがフォールトした場合、サーブ権は失われずパートナーである2人目のサーバーに移ります。そして、その2人目のサーバーもフォールトを犯した時点でようやく「サイドアウト」となり、サーブ権が完全に相手チームへと移動します。
ただし、繰り返しになりますが、ゲーム開始時の最初のサーブ権だけは、1回のフォールトでサイドアウトとなる特別ルールが適用されます。
シングルスの場合:
サーバーは1人しかいないため、サーバーがフォールトを犯すとその瞬間にサイドアウトとなり、直ちに相手にサーブ権が移ります。
重要ポイント:レシーブ側が勝っても得点にはならない
ピックルボールの戦略を考える上で最も重要な特徴の一つが、得点できるのはサーブ権を持っている側だけという点です。レシーブ側のチームがどれだけ素晴らしいプレーでラリーに勝ってもポイントは入りません。
その勝利は相手からサーブ権を奪い、自分たちが得点するチャンスを得るための権利、すなわち「サイドアウト」を獲得するだけにとどまります。この仕組みが1ポイントごとの攻防に深みを与えています。
サーバーはサーブを何回打つ?
「サーバーは一度のサーブ権で何回ボールを打てるのか?」という疑問は、特にテニスなど他のラケットスポーツ経験者からよく聞かれます。テニスではファーストサーブに失敗してもセカンドサーブのチャンスがありますが、ピックルボールのルールはよりシンプルかつ厳格です。
結論から言うと、ピックルボールでは各サーバーが自分の番でサーブを打てるのは1回のみです。ファーストサーブがネットにかかったり、アウトになったりして失敗(フォールト)した場合、セカンドサーブの機会は与えられません。
その時点で即座にフォールトとなり、サーバー交代(ダブルスの場合)またはサイドアウト(シングルスの場合)となります。
サーブは常に一発勝負!
セカンドサーブという保険がないため、1球1球のサーブには大きなプレッシャーがかかります。
そのため特に試合の重要な局面では、エースを狙うようなリスクの高いサーブよりも、スピードを抑えてでも確実に相手コートの深い位置に入れる、コントロール重視のサーブを選択することが賢明な戦略となります。
さらに、2021年のルール改正によりサービスレット(サーブがネットに触れてサービスエリアに入った場合のやり直し)は廃止されました。これによりサーブがネットに触れた場合でも、そのまま規定のエリアに入ればプレーは続行されます。
この改正はプレーを中断させることなく、よりスムーズな試合進行を促すためのものです。
ダブルスにおける「チームとしての」サーブ回数
ダブルスの場合、チーム全体として見るとサイドアウトまでの間にサーブの機会が2回あるように感じられます。これは1人目のサーバーがフォールトした後に、2人目のサーバーであるパートナーにサーブ権が移るためです。
しかし、これはあくまで「チームとしてのチャンスが2回ある」という意味であり、各プレーヤー個人にとっては「自分のターンで打てるサーブは1回きり」という原則に変わりはありません。この点を混同しないようにしましょう。
サーブ側のみに与えられる得点
ピックルボールのスコアリングシステムは、「サイドアウト制」というクラシックな方式を採用しています。これはかつてのバレーボールやバドミントンでも使われていたルールで、ピックルボールの戦略性を高める非常に重要な要素です。
サイドアウト制の核心はその名の通り、得点できるのはサーブ権を持っているチーム(またはプレーヤー)がラリーに勝った時だけという、非常にシンプルな原則に基づいています。
サーブ権を持たないレシーブ側のチームはたとえラリーに勝ったとしても、スコアボードの数字を動かすことはできません。レシーブ側の勝利がもたらす唯一の報酬は、相手からサーブ権を奪い取ること(サイドアウトさせること)なのです。
このルールによって、試合のポイントは以下のように動きます。
- サーブ側がラリーに勝利した場合 → サーブ側に1点が入ります。サーバーはサイドを交代し同じサーバーが続けてサーブを行います。
- レシーブ側がラリーに勝利した場合 → どちらのチームにも得点は入りません。サーブ権がレシーブ側に移動し、攻守が交代します(サイドアウト)。
つまり、得点を重ねるためには「まず守りで相手のサーブ権を奪い、次に攻めに転じて自分たちのサーブゲームでポイントを取る」という2段階のプロセスが必要になるわけです。この攻守の切り替えのうまさが勝敗を大きく左右します。
ピックルボールの試合は一般的に11点先取で行われます。ただし、スコアが10-10の同点(デュース)になった場合は、その後どちらかが2点差をつけるまでゲームは続行されます。
この得点システムを深く理解することで、サーブ権を持っている時の1ポイントの価値、そしてレシーブゲームでいかにしてサイドアウトを奪うかという戦略の重要性が見えてくるでしょう!
ピックルボールでサーブの順番を活かす戦略
- 相手を崩すサーブのコツ
- 初心者も安心のドロップサーブ
- 戦略的なレシーブの立ち位置
- ツーバウンドルールとボレーの関係
- ピックルボールのサーブの順番やルールについて総括
相手を崩すサーブのコツ
ピックルボールのサーブは、ルールによってアンダーハンドで、かつ打点が腰よりも低い位置に制限されているため、テニスのような時速200kmを超える弾丸サーブでエースを量産することはできません。
しかし、それはサーブが単調で重要でないという意味では決してありません。むしろ、緻密なコントロールと戦略的な工夫によって相手を効果的に崩し、ラリーの主導権を握るための極めて重要な第一打となります。
最も重要なサーブの基本:深く、そして確実に
あらゆる応用技術の土台となる最も大切なコツは、相手コートの深く、ベースライン際に安定してサーブをコントロールすることです。
短く浅いサーブは、相手に前進しながら攻撃的なリターンを打つ絶好の機会を与えてしまいます。相手をベースラインに釘付けにするような深いサーブは相手のリターンを難しくし、サーバー側に3球目攻撃の準備をする時間的余裕をもたらします。
まずはこの「深さ」を意識して練習することが、上達への最短ルートです。
回転を加えてボールに多彩な表情を
安定性が確保できたら、次はサーブに回転を加えてみましょう。ボールの軌道やバウンドを変化させることで相手のタイミングをずらし、リターンミスを誘発できます。
代表的な回転サーブ
- スライスサーブ:ボールの側面に横回転をかけるサーブです。ボールは利き腕と反対方向に曲がりながら飛び、バウンド後は低く滑るように変化します。相手をコートの外に追い出したり、苦手なバックハンドで打たせたりするのに非常に効果的です。
- トップスピンサーブ:ボールに強い前回転をかけるサーブです。ボールは山なりの軌道を描きながら相手コートで急激に落下し、バウンド後は高く前方に鋭く伸びます。相手の打点を詰まらせ窮屈な体勢でのリターンを強いることができます。
これらの回転をマスターするには、基本的なコンチネンタルグリップ(包丁持ち)から少し握りを調整し、ボールの表面を薄く擦る(ブラッシングする)感覚を養う必要があります。様々なコースや球種を組み合わせることで、相手に的を絞らせない予測不能なサーブが完成します。
サーブの戦略性を高める3つの視点
- コースを狙う:相手の弱点であるバックハンド側、ダブルスの場合はパートナー同士の真ん中、あるいは意表を突くボディサーブなど、戦略的にコースを打ち分けましょう。
- 緩急をつける:常に全力で打つのではなく、速いサーブの間にあえて山なりの緩いサーブを混ぜることで、相手のリズムを効果的に乱すことができます。
- 相手を観察する:試合を通して相手がどのようなサーブを嫌がっているかを注意深く観察しましょう。苦手なコースや球種を見つけたらそこを執拗に攻めるのがセオリーです。
このように、サーブは単にゲームを開始するための儀式ではありません。戦術の起点として次の展開を予測しながら、相手をいかにして崩すかを考え抜いて放つ一打なのです。
初心者も安心のドロップサーブ
「アンダーハンドサーブの腰より下で打つというルールが窮屈で難しい…」「打点の位置が合っているか不安で、思い切って振れない…」ピックルボールを始めたばかりの方の多くが、こうしたサーブの悩みに直面します。そんな初心者の方々にとってまさに救世主となるのが「ドロップサーブ」です。
ドロップサーブは一般社団法人日本ピックルボール協会(JPA)のルール概要でも紹介されている通り、2021年に正式に導入された比較的新しいサーブ方法です。その手順は驚くほどシンプルで、誰でもすぐに実践できます。
- ボールを持つ手を任意の高さからコート内に伸ばします。
- ボールを握らず、手のひらから自然に落下させます(ドロップ)。
- ボールがコートで一度バウンドしたところを好きなように打ちます。
このサーブの最大のメリットは、なんと言っても従来のアンダーハンドサーブに課せられている「インパクトは腰より下」「パドルのヘッドが手首より下」といった、複雑で厳しい打点の高さに関する規制が一切適用されない点です。
これによりプレーヤーは窮屈なフォームやルール違反の心配から解放され、ボールを確実に捉えることだけに集中できます。
ドロップサーブの注意点とデメリット
- ドロップ方法の制限:ボールを下に叩きつけたり、上にトスしたり、回転を加えたりしてドロップさせることは禁止です。あくまでも重力に任せて自然に落下させる必要があります。
- 相手への時間的猶予:ボールを一度バウンドさせるため、相手レシーバーはリターンの準備をするための時間的余裕が生まれます。そのため奇襲的な効果は薄くなります。
ドロップサーブはまず確実にサーブを入れてラリーを楽しみたい初心者の方にとって、これ以上ないほど有効な選択肢です。また、従来のサーブとドロップサーブは、同じゲームの途中であってもポイントごとに自由に使い分けて構いません。
まずはこのサーブで自信をつけ、徐々に従来のアンダーハンドサーブに挑戦していくという段階的なステップアップが、無理のない上達への道筋となるでしょう。
戦略的なレシーブの立ち位置
ピックルボール、特にダブルスの戦略においてサーブの順番と同じくらい、あるいはそれ以上に重要かつ複雑なのがレシーブ側の立ち位置です。
一見、自由に構えて良いように思えますが、実はスコアに応じて厳密に定められたポジションにつかなければならず、これを間違えるとフォールトを取られてしまいます。
このルールの根底にある原則は、非常に論理的です。
- 自チームのスコアが0または偶数の場合:プレーヤーはゲーム開始時と同じサイドでレシーブの構えをします。
- 自チームのスコアが奇数の場合:プレーヤーはゲーム開始時とは反対のサイドに移動し、パートナーとポジションを入れ替わってレシーブします。
なぜこのようなルールになっているのかというと、それはサーブ側が得点するたびにサーバーが左右のサイドを移動するのに対し、レシーブ側は得点に関わらずその場に留まるからです。
そのため、スコアが奇数になるタイミングでレシーブ側が意図的にサイドを入れ替わらないと、いざラリーに勝ってサーブ権を奪った際にプレーヤーが本来いるべきでないサイド(例:偶数スコアなのに左サイド)からサーブを始めなければならなくなり、ルール上の矛盾が生じてしまいます。
この矛盾を解消するための合理的なルールなのです。
最初は頭が混乱してしまいそうですが、「自分たちのスコアが奇数になったら、レシーブの時だけパートナーと場所を交代する!」と呪文のように覚えておくと、試合中のミスをぐっと減らせますよ。
この立ち位置の間違いは相手に無駄なポイントを与えてしまう痛恨のミスに繋がります。特にスコアが目まぐるしく動く試合展開では常に自分たちのスコアを確認し、正しいポジションを取る習慣をつけましょう。
| 自チームのスコア | プレーヤーAの立ち位置 | プレーヤーBの立ち位置 |
|---|---|---|
| 0, 2, 4, 6… (偶数) | ゲーム開始時のポジション | ゲーム開始時のポジション |
| 1, 3, 5, 7… (奇数) | ゲーム開始時と反対のポジション | ゲーム開始時と反対のポジション |
重要なこととして、このポジションチェンジはあくまでサーブをレシーブする瞬間に限定されたルールです。リターンのボールを打ち返した後は、プレーヤーはコート内を自由に動き、フォーメーションを変化させてラリーに対応することが許されています。
ツーバウンドルールとボレーの関係
すでにご紹介した「ツーバウンドルール」は、ピックルボールのゲーム性を根底から支えるまさに象徴的なルールです。このルールがサーブ後のラリー展開、とりわけボレーが可能になるタイミングを規定しており、ピックルボール特有の戦略的な駆け引きを生み出しています。
サーブからボレー解禁までの流れをもう一度詳しく見ていきましょう。
- 1球目(サーブ):サーバーが打ったボールは相手コートのサービスエリア内で必ず1回バウンドしなければレシーバーは返球できません。
- 2球目(リターン):レシーバーはバウンドしたボールを打ち返します。この返球もサーバー側のコートで必ず1回バウンドしなければサーバー側は返球できません。
- 3球目以降(ボレー解禁):このサーブとリターンの合計2回のバウンドが正規に完了した瞬間、両チームともにボレー(ノーバウンドでの返球)が全面的に解禁されます。ここからネットプレーを交えた本格的なラリーがスタートします。
この巧妙なルールのおかげで、テニスで一般的な「サーブ&ボレー」のように強力なサーブを打った直後にネットにダッシュし、相手の返球をノーバウンドで叩き込むという一方的な速攻戦術は成立しません。
ゲームの序盤では必ずグラウンドストローク(バウンド後の返球)の応酬が発生するため、初心者でもラリーに参加する機会が保証され、プレーヤー間の実力差が出にくいという生涯スポーツとしての特性が生まれています。
ツーバウンドルールの戦略的本質:「3球目攻撃」
このルールは守備的な側面だけでなく、攻撃の起点としても極めて重要です。特にサーバー側が打つ「3球目」は、試合の流れを決定づける最初の勝負どころとなります。サーバー側には主に2つの戦術的選択肢があります。
- 3rdショットドライブ:相手のリターンが浅く、チャンスボールになった場合に選択します。力強いドライブで相手の間を抜いたり足元に沈めたりして、一気に攻撃の主導権を握ります。
- 3rdショットドロップ:相手のリターンが深い場合に選択します。ネット際のノンボレーゾーンにふわりと落ちるような繊細なドロップショットを打ち、相手を前に引きずり出します。これを打った後、すかさず自分たちもネットに詰めることで、有利なネットプレーの展開に持ち込みます。
サーブの順番という手順だけでなく、この「3球目からゲームが本格的に動き出す」というピックルボール特有のリズムを体で覚えることが、単なるプレーヤーから戦略的なプレーヤーへと進化するための重要なステップとなるのです。
ピックルボールのサーブの順番やルールについて総括
ピックルボールのサーブの順番と、それに関連する重要なルールやコツについてより深く掘り下げて解説しました。複雑に見えるルールも、一つ一つの意味を理解すればすべてがゲームを面白くするための合理的な仕組みであることがわかります。
最後に、この記事で解説した要点をリストで再確認し、あなたのピックルボール知識を確かなものにしましょう!
- ピックルボールのサーブは常に1回のみでセカンドサーブのチャンスはない
- 得点機会はサーブ権を持つ側のみに与えられるサイドアウト制を採用している
- ダブルスのゲーム開始時は特別ルール「0-0-2」から始まり最初のサーバーは1人だけ
- サーブ権を獲得したチームは必ずその時点で右サイドにいるプレーヤーからサーブを始める
- サーバーは得点するたびに左右のサイドを交互に移動してサーブを継続する
- ダブルスでは1人目のサーバーがミスをしてもパートナーにサーブ権が移る
- シングルスのサーブ位置は自身のスコアが偶数なら右サイド奇数なら左サイドと決まる
- サーブとリターンの2球は必ずバウンドさせてから返球するツーバウンドルールがある
- ラリー3球目以降からネットプレーを含むボレーが全面的に解禁される
- ネット際のノンボレーゾーン内ではいかなる場合もボレーは禁止されている
- サーブの基本戦術は相手コートのベースライン近くを狙う深いコントロールが鍵
- 上級者はスライスやトップスピンなどの回転を加えてリターンミスを誘う
- 初心者やルールが不安な人には打点制限のないドロップサーブが強く推奨される
- ダブルスのレシーブ時は自チームのスコアが奇数になったらパートナーと立ち位置を交代する
- これらのルールを正確に理解し戦略的にプレーすることが勝利への最短ルートとなる
【関連】